
五臓六腑のそれぞれの役割を知りたい!
という方に向けて、この記事では、以下のことを解説していきます!
- 五臓六腑とは何か
- 五臓六腑のそれぞれの紹介
それではみていきましょう!
もくじ
五臓六腑とは何?
【五臓六腑にしみ渡る】という表現を耳にしたことはありませんか?
たまに聞くことがあるのですが、どんな意味なのでしょうか。
五臓六腑とは【はらわた。内臓。からだの中すべて】のことです。
もっと詳しくみていきましょう。
五臓六腑一覧
以下が、五臓六腑の一覧となります。
- 心臓
- 肺臓
- 秘蔵(ひぞう)
- 肝臓
- 腎臓
- 大腸
- 小腸
- 胃
- 胆(きも)
- 膀胱(ぼうこう)
- 三焦(さんしょう)
それぞれの役割についてみていきましょう。
五臓のそれぞれの役割一覧

まずは、五臓と呼ばれる臓器から見ていきましょう!
心臓について
心臓は血液循環の原動力になる器官です。
収縮と拡張を常に繰り返して、全身に血液を送るポンプの働きをします。
静脈から戻ってきた血液を今度は動脈へ送る。
にぎりこぶし程の大きさであり、胸のほぼ中央にあります。
肺臓について
肺臓は呼吸をおこなうための器官です。
胸の中央をはさんで、左右二つに分かれている構造です。
肺の中に空気の通り道である気管支があり、枝分かれして肺胞へと繋がります。
肺胞はブドウの様な形をしており、役割は、呼吸をしてガス交換をおこなうこと。
空気中の酸素を体内に取り入れ、二酸化炭素を排出します。
脾臓(ひぞう)について
脾臓は、にぎりこぶし大の柔らかい臓器で腹部の左上辺りに位置します。
白脾髄・赤脾髄(はくひずい・せきひずい)と呼ばれる2つの組織から形成。
白脾髄は、感染を防御する器官のひとつです。
リンパ球と呼ばれる白血球を作り、リンパ球は抗体(異物の侵入から守るタンパク質)を作るのが役割となります。
赤脾髄は、白脾髄の周りを包むような形状です。
また細菌やウイルスなどを消化する、食細胞と呼ぶ白血球を含んでいます。
赤脾髄の働きは以下の通りです。
- 赤血球の状態を監視する。正常でない赤血球を破壊する。
- 白血球や血小板などを貯蔵する
- 血液をろ過して不要物質を取り除く
肝臓について
肝臓はおなかの右上、横隔膜の下部で、胃の隣にあります。
1㎏から1.5㎏ある大型の臓器です。
肝臓の働きは以下の様になります。
- 糖分の貯留と放出。代謝の作用。
- 毒素の分解と排泄作用。
- アルコールやコレステロールを分解したり、体内の環境を整える
とても重要な役割をする臓器です。
上部に出来ており、よほどのことがないと症状が現れない臓器です。
そのため、【沈黙の臓器】とも呼ばれることも。
腎臓について
腎臓の位置は、腰の少し高い位置で背中側にあります。
背骨を挟んで左右に1個ずつあり、にぎりこぶしの大きさをした臓器です。
【肝心(腎)要】(かんじんかなめ)と言葉にもあるほどの大切な臓器です。
働きとしては
- 血液のろ過装置
- 老廃物や余剰な水分を排泄する
- 体内の水分量やイオンのバランスを調節する
- 血圧を調整して、赤血球をつくる
- ビタミンDを活性化させる。骨を丈夫にする。
など非常に重要な臓器です!
六腑のそれぞれの役割一覧

次に、六腑と呼ばれる臓器から見ていきましょう!
大腸について
大腸は水分・ミネラルを吸収して便を作る働きをします。
食後に便として排泄されるまでに、24時間~72時間必要です。
大腸の長さは1.5mと長く、盲腸、結腸、直腸に分けられます。
盲腸は退化しており、特に働きはありません。
結腸は便を作る働きをします。
また、小腸で消化できなかった食物繊維などを発酵させる。
直腸は便の貯蔵庫です。
便がたまると、肛門を開いて便を体外へ押し出す調節をします。
小腸について
小腸・回腸は胃や十二指腸で消化された食べ物を、分解して吸収する働きをします。
小腸・回腸を合わせて小腸と呼びます。
非常に長さのある臓器で、約6ⅿあるとも。
粘膜に無数の突起があって表面積が大きく、多くの栄養素を吸収できます。
胃について
胃は食物を消化する器官です。
食道から腸をつなぐ、袋状の形をした臓器です。
働きは以下のようになります。
- 食べたものを体内に貯めておく
- 食べたものを消化する
- 食べたものを、量を調節しつつ小腸へと送る
- 糖タンパク質を分泌する(ビタミンB12の吸収に必要)
胆(きも)について
胆のうであり、胆嚢と書きます。
肝臓で作られた胆汁(たんじゅう)を貯めておく働きをします。
胆汁とは脂肪を消化するのに必要な液で、1日に1㍑生成されます。
脂肪の取りすぎで石ができ、固まって結石すると【胆石】という病気になります。
膀胱(ぼうこう)について
膀胱はおへその下あたりにある、風船のような形をした臓器です。
腎臓から絶えず流れ出てくる尿を貯めておきます。
そのまま尿のたまる量によって膨張し、ある程度の量になると排出するのが役割です。
膀胱の容量は300~400mlで、尿が150~200mlほど溜まると尿意を催すようになっています。
三焦(さんしょう)について
三焦とは横隔膜を中心として上焦・中焦・下焦に分かれて位置する器官です。
上焦は心や肺を含み、中焦は胃を含む。
下焦は小腸・大腸や腎臓を含み、それぞれ気の移動経路です。
気の流れ「元気」は腎から三焦を通って全身へと広がって、各臓器の機能を維持するとされます。
まとめ
以上が五臓六腑の解説でした。
臓器の大まかな役割を知って、体が健康であることの大切さを感じました。
腎臓や肝臓は特に大切な臓器。
日頃の食事やお酒も、暴飲暴食は控えないといけませんね!

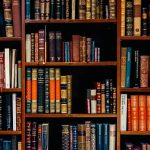

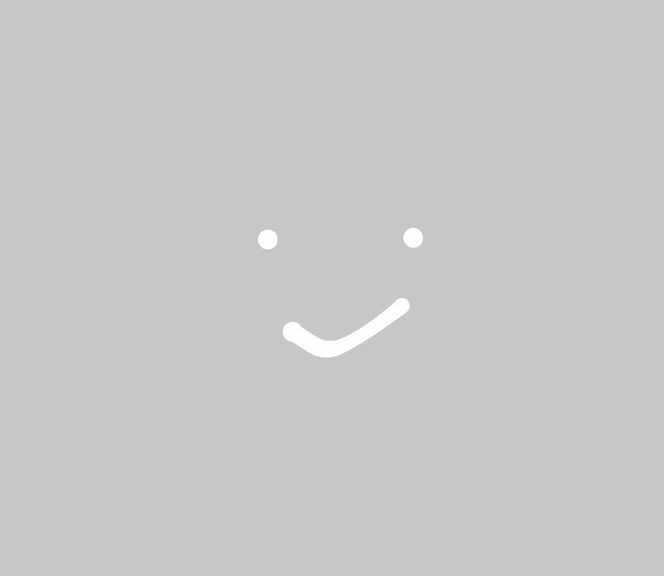
五臓六腑ってなんのことなの?